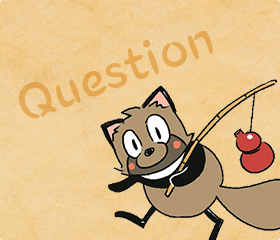ホーム > 文化・観光・スポーツ > 文化・芸術 > 文京ふるさと歴史館 > 利用案内 > 文京ふるさと歴史館友の会とは
更新日:2024年5月5日
ページID:4169
ここから本文です。
文京ふるさと歴史館友の会とは
文京ふるさと歴史館友の会は平成3年、文京ふるさと歴史館開館と同じ年に結成されました。
文京区の歴史や文化、人々の暮らしについて、研究やボランティア活動を行っています。
会員の会費を財源として会を運営しており、その事業運営は会員のボランティア活動によって支えられています。
主な活動
詳細は、活動内容をご覧ください。
- 区内のほか都内各所の史跡を巡る学習会
- 歴史と文化についての講演会
- 文京まち案内ボランティア活動
- 文京ふるさと歴史館常設展示ボランティアガイド活動
- 研究部会による調査・研究活動
- 「友の会だより」の編集・発行
お問い合わせ先
アカデミー推進部アカデミー推進課文化資源担当室(文京ふるさと歴史館)
〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目9番29号
電話番号:
03-3818-7221
ファクス番号:03-3818-7210